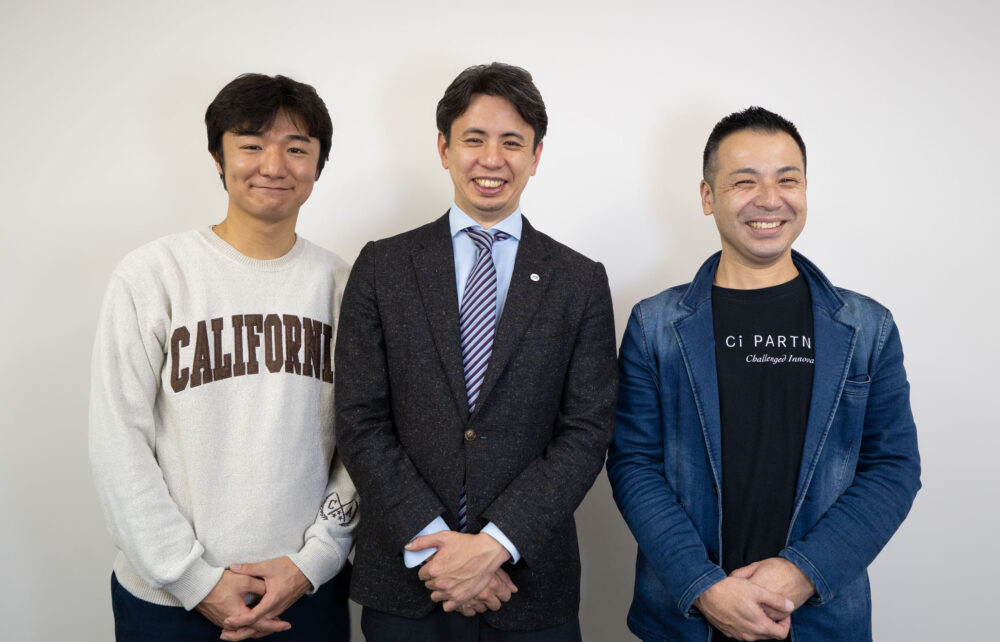子どもの発達支援を考えるSTの会 会報15号『みんなで創る子どもST』に寄稿しました
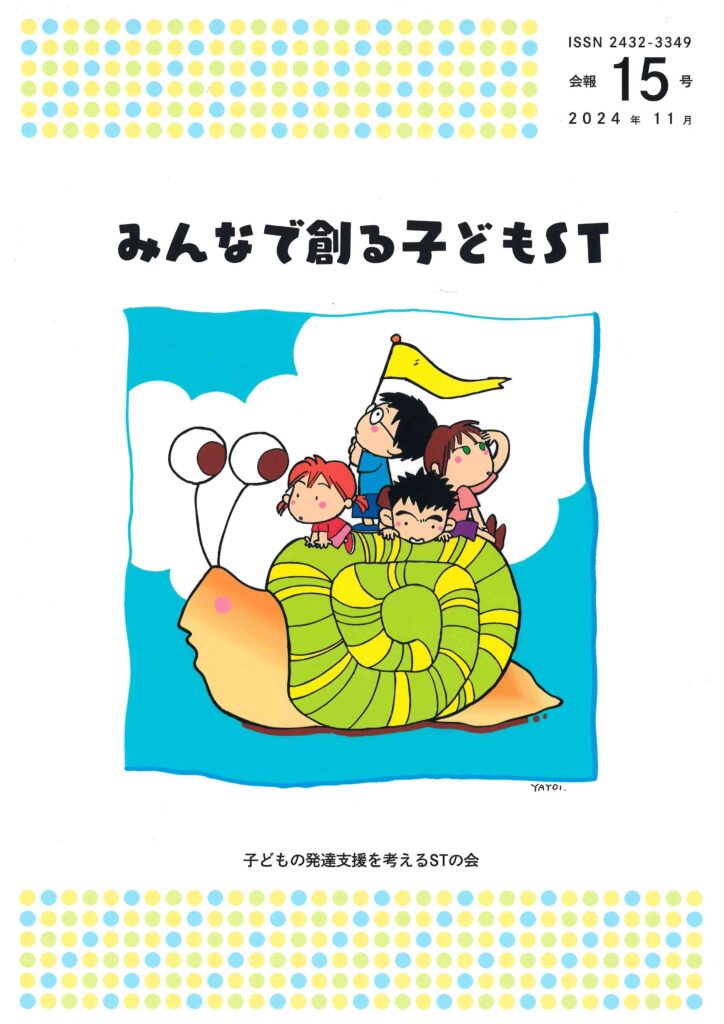
2024年11月発行、子どもの発達支援を考えるSTの会 会報15号『みんなで創る子どもST』に代表取締役の家住教志が寄稿しました。
子どもの発達支援を考えるSTの会では、子ども分野のST(言語聴覚士)の認知度向上と活躍の場を広げるための活動のひとつとして、全国研修会の報告や会員からの投稿、各地の取り組みなどをまとめた会報を毎年発行されています。
今回は、代表家住のご息女の療育にてお世話になった、関西福祉科学大学講師で言語聴覚士の工藤先生より、同誌の連載企画「教育講座・当事者の視点」への寄稿をご依頼いただきました。
STの役割は、ことばや聴こえの発達を支援し、機能回復や現状維持を目指すことにあります。しかし、そのような障がいのある方が将来、社会の一員として自立し働くためには、機能面の支援に留まらず、その先にある課題にも目を向ける必要があります。たとえ機能の維持や向上が図られ、一定の学歴を得たとしても、対人スキルやメンタルスキルといった社会的スキルが備わっていなければ、就職や就労の継続は難しいからです。
特に、障がい者雇用においては、学歴よりも社会的スキルが重視される傾向があります。そのため、多くの方が就職というステージに立つこと自体に課題を抱えています。せっかく話せるようになったとしても、活かす場や機会が得られなければ、その力を十分に発揮することはできません。
こうした背景から、STが担う言語や聴覚、発声・発音、認知といった機能面の支援とその先の就労支援を接続するべく、当事者の親であり、児童発達支援事業所や放課後等デイサービスも運営する就労支援事業者としての視点でメッセージを寄せる機会をいただきました。
本稿では、「学齢期からの就労支援」をテーマに、代表家住が障がい福祉に携わるようになったきっかけやその実態を見て感じた様々な課題、将来を見据えた就労支援の必要性と福祉施設の役割、そして学齢期から就労支援を受けた方の事例を紹介しています。
この機会にぜひ『みんなで創る子どもST』をご覧いただき、貴会の取り組みや弊社の支援の在り方へのご理解を深めていただければ幸いです。
会報の詳細については、以下URLよりご確認ください。
https://kodomost.jp/bulletin.html#top
▼購入ページはこちら
https://escor.co.jp/products/products_item_books_kodomost_kaihou.html
子どもの発達支援を考えるSTの会
2022年に活動を開始した国内最大級の子どもSTコミュニティ。療育機関や相談機関、病院、保健センター(保健所)、学校などで子どもの発達支援にかかわるSTが知恵やノウハウを共有する”ひろば”として、様々な活動を行っている。(ホームページはこちら)